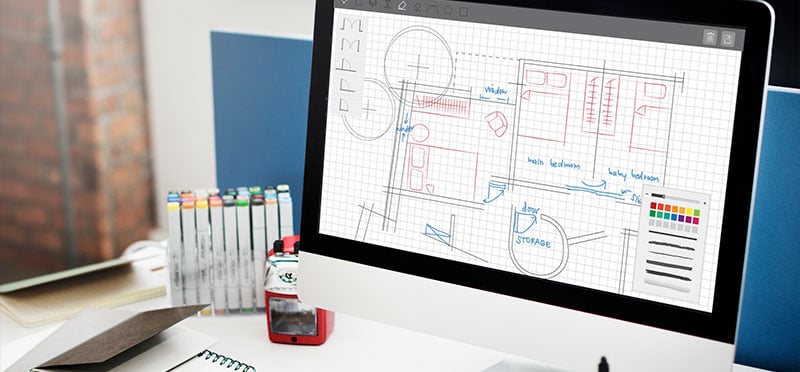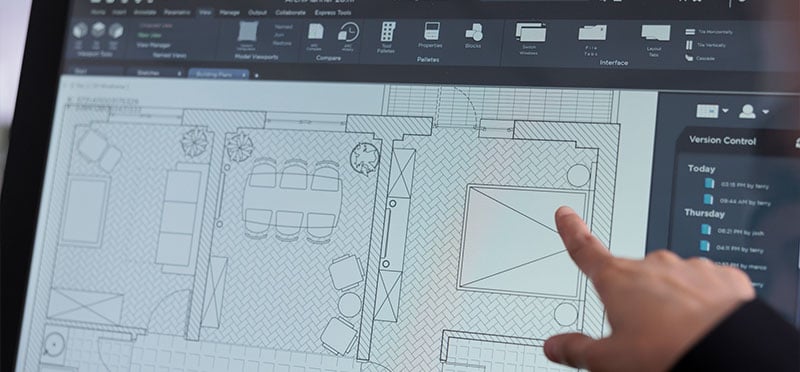建築業界では「建築士」と「設計士」という言葉をよく耳にしますが、両者の違いについて詳しく知っている人は少ないでしょう。建築に関わる仕事には複数の役割があり、それぞれに異なる専門性や資格が必要とされています。
建築士と設計士の基本的な違い
建設業界で活躍する二つの職種には大きな違いがあります。法律で定められた国家資格を持つプロフェッショナルと、専門的な知識を持つサポート役という明確な区分があり、業務範囲や目指すべきゴールまで異なっているのです。
建築士とは何か
厳格な国家資格制度に基づいて定められているのが建築士です。一級・二級・木造の3つの区分があり、建築物の設計から工事監理まで幅広い業務を行います。法律によって独占業務が明確に定められ、建設業界の中でも特に責任の重い立場として認識されている職業です。
設計士とは何か
建築関連の知識を持ち、建築業界で働くスペシャリストとして位置づけられています。主に建築士のサポート業務を担当し、図面作成から書類管理まで幅広い実務をこなします。100平方メートル未満の木造建築物であれば、単独で設計できる権限があるのが特徴的な職種です。
建築士と設計士の役割の違い
建設プロジェクトの中で担う責任の重さに大きな違いがみられます。建築士は設計から施工管理まで全体を統括し、施主との交渉から行政への申請手続きまでを担います。一方、設計士は建築士の指示のもと図面作成や書類管理などの実務作業を担当する立場になります。
建築士と設計士の仕事内容

資格の有無によって大きく異なる業務範囲は、施主との打ち合わせから竣工まで、それぞれ独自の専門性を発揮しながら進められています。双方が密接に連携し合うことで、建設プロジェクトは円滑に遂行されていくのです。
建築士の具体的な業務内容
施主の要望を丁寧にヒアリングし、それを実現可能な設計図面へと落とし込んでいきます。構造計算や法規制の確認など、高度な専門知識と技術的判断が必要な業務を担当し、施工段階では現場監理も行います。建物の安全性と品質を確保する重要な立場として、多岐にわたる業務をこなしています。
設計士の業務内容とプロセス
建築士の指示のもと、CADソフトを使用した図面の作成から修正作業までを担当します。施主との打ち合わせに同席して議事録を作成したり、建築確認申請などの行政手続きに関する書類作成を担当したりします。実務のプロフェッショナルとして、建設プロジェクトの円滑な進行を支えています。
両者の担当分野の違い
規模や構造によって明確に担当できる建築物の範囲が決められています。高層ビルや大型施設は一級建築士の独占業務となり、住宅や小規模店舗は二級建築士が担当できます。設計士は小規模な木造建築物や建築士の補助業務を中心に担当し、経験を積みながらスキルアップを目指します。
年収の違いとその要因
業務内容や責任の重さの違いは、収入面にも大きく反映されています。国家資格保有者とそうでない場合で年収に大きな開きが生まれ、キャリアアップの道筋も異なってきます。将来的な収入を考える上で、建築士の資格取得は重要な要素となっています。
建築士の年収
国家資格を保持する立場として、平均的な年収は600万円から800万円の範囲で推移しています。企業規模が1000人を超える大手企業では、月給が約51万円、賞与が年間228万円程度となり、年収が1000万円を超えるケースも珍しくない職種として知られています。
設計士の年収
一般的な年収は350万円から450万円の範囲で推移しています。勤務先の規模や経験年数によって大きな変動があり、大手企業でも500万円程度が上限となることが多いのが現状です。キャリアを積むことで徐々に収入は増えますが、建築士との差は歴然としています。
年収に影響を与える要因
勤務先の企業規模や所在地によって基本給に大きな差が出ます。実務経験の年数や実績に応じて昇給する仕組みがあり、資格取得によるステップアップで収入を増やすことができます。特に一級建築士の資格を取得すると、年収が大きく跳ね上がる可能性が高くなります。
求められるスキルと能力
建築業界の第一線で活躍するために必須となる専門的な技能と人間性について詳しく解説していきます。デザインから施工まで幅広い知識を持ち、柔軟な発想力とコミュニケーション力を備えることで大きく成長できる職種です。
建築士に必要なスキル
専門的な知識に基づいて建築物の設計や施工管理を行うため、構造力学や建築基準法の理解が欠かせません。法令順守の観点から建築確認申請の手続きにも精通し、建物の安全性を確保する技術力と判断力が求められています。
設計士に求められる能力
図面作成やCADオペレーションの技術はもちろんのこと、施主の要望を正確に理解し、それを図面に反映させる表現力が大切です。建築士の補助業務を通じて実践的なスキルを磨きながら、デザインセンスを高めていきます。
両者に共通する重要なスキル
建築物の空間を立体的に把握できる能力と、それを図面化できる表現力は両職種に共通する基本スキルとなっています。施主や職人との打ち合わせを円滑に進めるためのコミュニケーション力も必須の要素となっています。
資格取得の方法と難易度

建築業界で地位を築くうえで避けて通れない資格取得について解説します。それぞれの立場によって目標となる資格は異なりますが、段階を踏んでキャリアアップを目指すことができます。
建築士試験の流れと対策
一級建築士の合格率は毎年10%前後と非常に厳しい水準になっています。学科試験と製図試験の2段階で実施され、理論と実践の両面から高度な専門性が問われる試験内容となっています。
設計士試験の難易度と準備
設計士という資格は存在せず、職務上の呼称として使われています。そのため、特別な試験はありませんが、建築業界で働くうえでCAD検定などの実務に関連する資格を取得しておくと有利です。
試験を受けるための条件
一級建築士は大学などで指定科目を修了後、実務経験2年以上が必要です。二級建築士は学歴に応じて実務経験の要件が異なり、建築系の学校を卒業していれば実務経験なしでも受験可能となっています。
バックグラウンドと必要な学歴
建築の仕事に就くための教育背景は多岐にわたります。専門的な知識を身につけるための学びの場として、それぞれの特徴を活かした教育機関が存在しており、目的に応じて選択できます。
建築士に必要な学歴
建築士になるためには、大学や専門学校で建築に関する指定科目を履修する必要があります。建築学科や工学部建築工学科などで、設計や構造計算、建築法規といった専門知識を体系的に学んでいきます。
設計士としての進学先
建築系の専門学校や大学で学ぶ場合が多く、CADや設計の基礎知識を習得することができます。資格がなくても実務経験を積むことで、100㎡未満の木造建築物の設計に携わることも可能となっています。
専門学校と大学の役割
専門学校では実務的なスキルを重視したカリキュラムが特徴です。一方、大学では理論的な学習に重点が置かれ、より幅広い知識を身につけることができます。就職後のキャリアプランに応じて選択することが望ましいでしょう。
女性が活躍する職場環境
建設業界における女性技術者の数は年々増加傾向にあります。特に木造住宅の分野では、住まい手目線のきめ細やかな対応力を活かし、女性の活躍が広がっています。育児との両立支援や、柔軟な働き方の導入で、さらなる成長が期待されています。
建築士としての女性の現状
女性の建築士資格取得者は着実に増加しており、令和5年度の女性建築士の人数は全体の12%を占めています。特に住宅設計の分野では住まい手の気持ちに寄り添える女性建築士の活躍が目立っており、家族構成や生活スタイルに応じた提案力に定評があります。
設計士としての女性のキャリア
家族の暮らしに寄り添う視点から、住宅設計の分野では女性の活躍が顕著です。リフォーム案件では、生活者の視点を活かした使い勝手の良い設計が高い評価を得ており、女性ならではのきめ細やかさを活かした仕事ぶりに注目が集まっています。
業界における男女比と活躍の場
建設業界全体では女性の比率が少ないものの、住宅メーカーや設計事務所では女性の採用に力を入れています。特に戸建て住宅やマンションの設計分野では、女性ならではの視点を活かしたプランニングが高く評価されています。
キャリアパスと仕事のやりがい
建築業界でのキャリア形成には、さまざまな可能性が広がっています。資格取得や実務経験を重ねることで、独立開業や専門分野のエキスパートとして活躍できる道が開けます。個人の志向や能力に合わせた成長を実現できる環境があります。
建築士のキャリアの選択肢
建築士の資格を取得すると、住宅メーカーや設計事務所での勤務から独立開業まで幅広い選択肢が広がります。構造設計や意匠設計といった専門分野に特化したり、工事監理のスペシャリストとして活躍したりと、自分らしいキャリアを築けます。
設計士のキャリアの可能性
実務経験を積みながら建築士資格の取得を目指すことができ、段階的なキャリアアップが可能です。小規模木造建築物の設計からスタートし、建築士のサポート業務を通じて経験を積むことで、より大規模なプロジェクトに携わることができます。
両者のやりがいと満足度
依頼主の夢を形にする喜びや、完成した建物を見た時の達成感など、建築の仕事ならではのやりがいがあります。地域のシンボルとなる建造物や、住む人の人生に関わる住宅づくりを通じて、社会に残る価値を生み出せる仕事です。
まとめ
建築士と設計士は、建築物の設計という点では共通していますが、資格や担当できる業務範囲、年収に大きな違いがあります。建築業界で活躍するためには、自身の目標や適性に合わせて、キャリアパスを選択することが大切です。
◤カグポン◢◤
家具業界初の営業効率化ツール
家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!
▼詳細はこちら
https://www.kagupon.com/