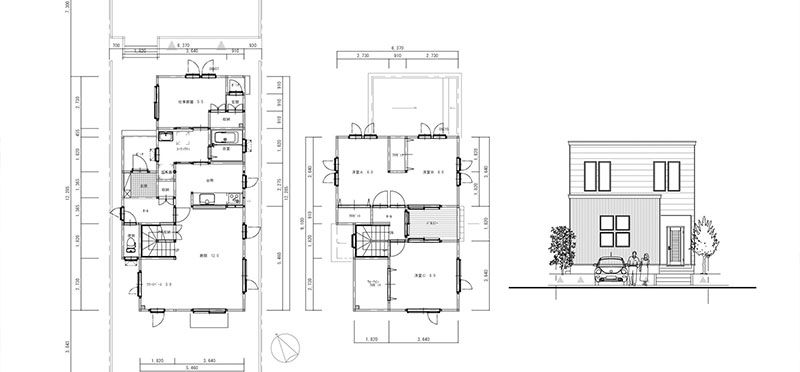営業設計職は一般的な営業職や設計職と比べて収入面でどのような特徴があるのでしょうか。両方のスキルを持つ人材への需要が高まる中、年収や手当の実態、転職市場での評価について詳しく見ていきます。
営業設計職とは?ハウスメーカーにおける役割

家づくりの窓口と技術提案を一人で担う営業設計職は特徴的な存在です。通常分かれている二つの役割を兼任することで、お客様の要望を直接形にしやすい利点があります。顧客満足度を高める鍵となる職種として近年注目されています。
営業と設計の違いとその重要性
従来のハウスメーカーでは顧客対応を行う営業と図面化する設計が分業制でした。両者の連携がスムーズに行われることで理想の住まいが実現します。二つの職種はそれぞれ専門性が高く、相互補完で質の高い住宅提供が可能になります。
営業設計職の仕事内容とは
営業設計職は集客からヒアリング、図面作成、プラン提案、工事関係者との調整まで幅広く担当します。技術知識とコミュニケーション能力の両方が必要です。お客様の住宅購入に最初から最後まで寄り添い、理想の家づくりを実現するサポート役となります。
ハウスメーカーで求められる営業スキル
住宅は人生最大の買い物とされるため、信頼関係構築が最重要です。顧客の要望を的確に理解し、住宅に関する専門知識を分かりやすく説明できる能力が求められます。さらに予算計画の相談にも応じられる財務知識や、提案力、問題解決能力も必要となります。
ハウスメーカーの営業と設計が仲悪い理由
大手ハウスメーカーでは営業と設計の対立が起きやすい構造があります。営業は顧客要望を重視する一方、設計は技術的観点から判断するためです。両者の優先事項や評価基準の違いから生まれる摩擦が、チームワークを妨げる要因になっています。
営業と設計のコミュニケーション課題
伝言ゲームのように情報が正確に伝わらないことが大きな問題です。営業がヒアリングした顧客の要望が設計に十分伝わらず、誤解が生じます。専門用語の理解度差や、認識のズレが原因となり、再設計の手間が増えるためお互いの不満が積み重なるのです。
業種ごとの営業と設計の関係性
住宅業界では営業主導型が多く、設計はサポート役になりがちですが、設計事務所では設計主導で進みます。製造業では両者が対等に意見交換する文化もあり、業種によって主導権や意思決定プロセスが異なるため、それぞれに適した連携方法を見つける必要があります。
仲悪い関係を改善するための手法
顧客情報の共有プラットフォームを活用し、両部門が同じ情報を見られる環境を整え、定期的な合同ミーティングを行いましょう。相互理解を深めるための部門間交流や、成功事例の共有、共通の目標設定によって協力関係を築けます。
営業が設計を担当するメリット
顧客の要望を直接聞いた人が設計することで、情報伝達のロスがなくなります。要望と提案の一貫性が保たれ、修正回数が減少するため効率的です。顧客視点と技術的視点の両方を持ち合わせることで、バランスの取れた住宅提案ができるようになります。
顧客との距離を縮める設計折込営業の利点
お客様と直接対話しながら設計を進められるのでリアルタイムで図面修正の提案ができ、意思決定がスピーディです。信頼関係が深まりやすく、顧客満足度が高まります。一貫したサポートにより安心感を与え、アフターフォローも充実させられます。
設計士と協力することで得られる実績
複雑な構造計算や法規制対応など専門知識が必要な場面では、設計士との協力が不可欠です。両者の強みを活かした連携により、技術的にも顧客満足度においても高いレベルの住宅提供ができます。
住宅業界における強みの活用
営業と設計のスキルを併せ持つことで、住宅提案の幅が広がります。専門知識を活かした説得力のある提案ができ、競合との差別化にもつながります。顧客の住まい方をより深く理解し、ライフスタイルに合った提案ができるのは大きな強みです。
設計事務所への営業方法のポイント

設計事務所へのアプローチは一般消費者向けとは異なります。専門家同士の対話となるため、技術的な知識や業界理解が必須です。設計事務所の課題やニーズを理解し、具体的な解決策を提示できると信頼を得やすくなります。
設計事務所との関係構築の重要性
一度の取引で終わらせず、継続的な価値提供を心がけましょう。定期的な情報交換や業界動向の共有など、ビジネスパートナーとしての関係構築が受注につながります。実績を積み重ねることで紹介案件も増えていきます。
効果的な営業戦略と提案方法
設計事務所には具体的なメリットを数値で示すことが効果的です。自社製品やサービスの強みを明確に伝え、設計業務の効率化や付加価値向上につながる提案をしましょう。実例や事例を用いた説明で説得力を高め、専門用語を適切に使うのもよいでしょう。
計事務所のニーズを理解するコツ
予算制約、工期短縮、差別化要素の追求など、様々な悩みがあります。事前リサーチを徹底し、個々の事務所の特徴や得意分野を把握しましょう。質問力を磨き、本当のニーズを引き出す対話を心がけることが成功の鍵です。
求められる経験とスキル
営業設計職には多様なスキルが求められます。住宅の構造や設備に関する知識はもちろん、コミュニケーション能力やプレゼン力も必要です。顧客の潜在ニーズを引き出す質問力や、予算内で最適な提案をするコスト感覚も重要となります。
建築設計に必要な知識と資格
建築基準法や都市計画法などの法規知識は必須です。二級建築士などの資格があれば有利ですが、未取得でも実務経験で補えます。構造や材料、設備に関する基礎知識や、CADなどの設計ツールの使い方も求められます。住宅性能や環境配慮の知識も役立ちます。
営業職としての成長に必要な経験
顧客との商談経験を積みましょう。様々なタイプの顧客対応を経験し、ニーズ把握力を磨きます。成約に至るまでの一連のプロセスを繰り返し経験することで、提案力や交渉力が向上するので、先輩社員の同行や勉強会への参加もしましょう。
オンライン・オフラインのスキル比較
対面での提案力が従来は重視されてきましたが、現在はオンライン対応も必須です。リモート商談ではデジタルツールの活用力や画面越しの説明技術が必要です。一方で模型や素材を使った体感型提案など、オフラインならではの強みを活かすスキルも磨きましょう。
営業設計職の年収と待遇
営業設計職の年収は企業規模や地域で差があり、大手ハウスメーカーでは平均600万円前後です。実力次第でさらに上を目指せ、成果によって収入アップが可能です。働き方改革により福利厚生も充実してきており、総合的に待遇改善が進んでいます。
営業マンと設計士の収入比較
営業職は成績連動のインセンティブがあるため、トップ営業マンの年収は設計士を上回ることが多いです。設計士の平均年収545万円に対し、営業マンは実績次第で600~800万円も可能です。ただし設計士は一級建築士取得後に収入が安定する傾向にあります。
優遇や手当の実態
営業設計職では基本給に加え、資格手当や成績インセンティブが設けられています。一級建築士は20~30万円、二級建築士は5~10万円の資格手当が多いです。FPや宅建などの資格でも手当が増え、住宅手当や社用車など福利厚生も充実してきました。
給与水準と昇給のトレンド
住宅業界の給与は緩やかに上昇中で、特に設計営業職は人材不足から待遇改善が進んでいます。新卒時350~400万円が5年で500万円前後、ベテランなら600~700万円が相場です。評価制度は年功序列から実力主義へシフトしており、成績次第で昇給幅が変わります。
転職する際のポイントと注意点
建築業界での転職は専門性を活かせることが強みです。経験やスキルを明確にアピールし、転職理由を前向きに伝えましょう。企業の社風や業務範囲をしっかり確認して自分に合った環境を選ぶことが、長期的なキャリア形成につながります。
新着求人を見つけるためのシンプルな方法
建築業界専門の転職サイトやエージェントを活用しましょう。業界特化型エージェントは非公開求人も多数保有しているため、複数に登録して情報収集をします。企業の採用ページや建築関連SNS、業界交流会への参加も新たな求人情報獲得につながります。
面接でのアピールポイント
営業設計職の面接では設計力と提案力の両方をアピールしましょう。設計実績だけでなく顧客折衝の経験も具体的に伝え、数字で示せると説得力が増します。「顧客の理想を形にする喜び」といったやりがいも語れば仕事への姿勢が伝わり、採用担当者の印象に残ります。
転職活動の時期とタイミング
住宅業界の転職は1~3月と9~10月が求人のピークです。年度末から新年度にかけては採用が活発化します。転職活動は3~6ヶ月の期間を見込み、余裕をもって始めるのが理想的です。在職中なら繁忙期を避け、計画的に有給休暇を活用して面接に臨みましょう。
設計部門と営業部門の連携を強化する方法
両部門がお互いの仕事内容や制約を理解することが基本です。定期的な情報共有会議や、合同での顧客訪問などの機会を設けましょう。共通の評価指標を設定し、部門間の壁を越えたチーム意識を育てることで、顧客満足度と業務効率の両方が向上します。
部門間の合意形成を図るためのヒアリング
各部門の課題や要望を定期的に聞く場を設けましょう。率直に意見交換できるように、「何のために」「何を」改善したいのかを明確にし、両部門が納得できる解決策を一緒に考えます。相互理解を深めるプロセス自体が連携強化につながります。
成功事例から学ぶ連携のポイント
連携がうまくいった事例を社内で共有しましょう。何がうまくいったのか、どんな工夫があったのかを分析します。成功要因を明確にし、他のケースにも応用できるようにします。失敗事例からも学び、改善点を見出すことで、より効果的な連携方法を確立できます。
共有するべきデータと情報の管理
顧客情報やプロジェクト進捗状況は必ず共有しましょう。アクセスしやすい情報共有システムを導入し、リアルタイムで情報が更新される環境を整えます。情報の更新ルールを明確にし、誰がいつ何を入力するか責任を明確にします。
業務の効率化と時間管理
営業設計職は業務範囲が広いため、効率化が欠かせません。優先順位づけやタスク管理を徹底し、必要に応じて業務の一部を外部委託することも検討しましょう。デジタルツールを活用し、日々の業務を見直すことで、顧客対応の質を落とさず効率アップが可能です。
受注プロセスの見直しと改善策
現状の受注プロセスを可視化し、ボトルネックを特定しましょう。無駄な承認手続きや重複作業を排除し、フロー全体の最適化を図ります。顧客にとって価値のある部分には時間をかけ、それ以外は簡略化する視点が大切です。
時間を有効活用するための工夫
1日の始めに計画を立て、優先度の高いタスクから着手します。集中作業と休憩のリズムを作り、生産性を高めましょう。顧客との面談時間は事前に設定し、目的を明確にすることで効率的な商談が可能になります。
営業部での業務管理ツールの活用
スケジュール管理やCRMツールを導入し、顧客情報や商談履歴を一元管理しましょう。クラウド型であればどこからでも設計作業やプレゼン準備ができます。部門内での情報共有ツールも活用し、類似案件の資料を再利用することで作業効率が向上します。
まとめ
営業設計職は専門性と営業力を併せ持つ貴重な人材として評価されています。転職では両方の経験をアピールし、自分に合った企業文化を見極めることが大切です。業界動向を押さえながら計画的に行動すれば、キャリアアップの大きなチャンスとなるでしょう。
◤カグポン◢◤
家具業界初の営業効率化ツール
家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!
▼詳細はこちら
https://www.kagupon.com/